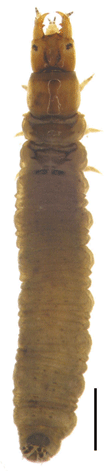 |
キイロヒラタガムシ3齢幼虫. 大顎は左右不対称. 腹部の側面には目立った突起はない.腹脚があり,イモムシのように歩く.顕微鏡で観察すると,腹脚には爪状の突起がある. スケール1mm. |
 |
キベリヒラタガムシ幼虫. 2齢幼虫と思われる. 基本的な構造はキイロヒラタガムシと同じ.頭部が濃い茶色をしており,オレンジ色のキイロヒラタガムシとは異なる. スケール1mm. |
 |
キイロヒラタガムシの成虫. 水田でよくみられ,幼虫も一緒に見つかることが多い. |